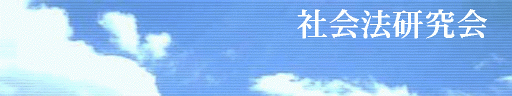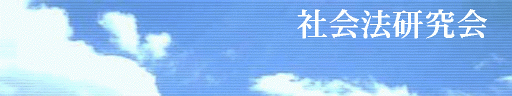7月
● 7月1日
- 湊 栄市 (北海道大学大学院)
- JR北海道(転勤命令)事件 札幌地判 平成17年11月3日 労判909号14頁
- JR東海関西支社(配転)事件 大阪地判 平成17年5月11日 労判900号75頁
- 家田 愛子 (札幌学院大学)
- 成田労基署長(日本航空)事件 千葉地判 平成17年9月27日 労判907号46頁
くも膜下出血による労災申請事件
● 7月8日
- 鈴村 美和 (北海道大学大学院)
- O法律事務所(事務員解雇)事件 名古屋高判 平成17年2月23日 労判909号67頁
法律事務所職員の配偶者が、相対立する立場の法律事務所に勤務する弁護士である場合、抽象的な可能性の問題としては、情報漏洩等の危険性を完全に否定できないが、当該事務員は、職務上知り得た事実について、弁護士と同等ではないとしても、当然に一定の雇用契約上の秘密保持義務を負っているのであり、通常はこの義務が遵守されることが期待できるというべきであるとされた例
- 三浦 保紀 (北海道大学大学院)
- 安威川生コン工業事件 最三小判 平成18年4月18日 公刊物未登載 〔→裁判所〕
会社が行ったロックアウトが正当とされ、その期間中の賃金支払い義務はないとされた事例。
- 控訴審 大阪高判 平成14年12月27日 公刊物未登載
- 第一審 大阪地判 平成7年2月27日 労経速1566号3頁
● 7月15日
- 平賀 律男 (北海道大学大学院)
- 遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件 東京高判 平成17年5月31日 判時1912号3頁
- 厚生年金の被保険者と内縁関係にあった者であっても,被保険者と近親婚の関係にあるものは,遺族厚生年金の受給権者たる資格を有しないとされた事例
- 倉田 聡 (北海道大学)
- ドイツ法における「社会保険(Sozialversicherung)」概念をめぐる議論と疾病保険法における〈連帯〉の変容
● 7月22日
- 久慈 亨 (北海道大学大学院)
- 第一工業事件 東京地判 平成18年3月10日 労経速1933号19頁
- 横領の事実がなく懲戒解雇は無効だが、横領の主張には現金管理者の責任を問う通常解雇の主張を含むとし、以前にした通常解雇は有効とした例
- 安部 薫道 (北海道大学大学院)
- NTT西日本(D評価査定)事件 大阪地判 平成17年11月16日 労判910号55頁
- 職種転換をともなう配転によって営業職となった原告らにつき、紛争処理制度を完備していないなどといった本件評価制度の問題点が、原告らに対する最低評価査定の違法性に直接関連するとは認められず、本件D評価が同評価制度に基づく評価であることをもって、不法行為を認めることはできないとされた例
- 辻村 昌昭 (淑徳大学)
- 韓國船級事件 神戸地判 平成17年9月28日 労経速1924号3頁
- 約17年間にわたり繰り返し更新されてきた有期雇用契約の期間途中の解雇が有効とされた例
● 7月29〜31日 《クールセミナー》
- 中内 哲(熊本大学)
- オリエンタルモーター(賃金減額)事件 東京地判 平成18年1月20日 労判911号44頁
- 淺野 高宏 (弁護士)
- 日音事件 東京地判 平成18年1月25日 労判912号63頁 労経速1930号3頁
- 浜村 彰 (法政大学)
- 根本 到 (神戸大学)
- 道幸 哲也 (北海道大学)
- 倉田 聡 (北海道大学)
- 藤川 久昭 (青山学院大学)
- テザック厚生年金基金事件 大阪高判 平成17年5月20日 労判896号12頁
8月
● 8月26日
- 鈴木 真史 (北海道大学大学院)
- ネスレ日本(配転本訴)事件 大阪高判 平成18年4月14日 労判915号60頁
- 精神病の妻や要介護者の母をもつ従業員らへの配転命令を権利濫用とした原審を維持した例。
- 國武 英生 (北海道大学大学院)
- 新国立劇場運営財団事件 東京地判 平成18年3月30日 労経速1936号18頁/労判918号55頁
- 期間1年とする合唱団メンバーの出演契約は労基法が適用される労働契約ではないとして、地位確認請求等が棄却された例。
- 橋本 孝夫 (北海道大学大学院)
9月
● 9月2日
- 佐久間 ひろみ (北海道大学大学院)
- 情報・システム研究機構(国情研)事件 東京地判 平成18年3月24日 労判915号76頁
- 本件事情の下では、任期付き国家公務員非常勤職員の任用更新拒絶は社会通念上是認しえないとして、継承法人との間の労働契約上の地位確認請求及び賃金請求が認容された例。
- 大石 玄 (北海道大学大学院)
- 広島県ほか(教員・時季変更権)事件 広島高判 平成17年2月16日 労判913号59頁
- 時季変更権の行使が適法にされたことを前提とする原告の就労義務は存在せず、したがって同日につき欠勤として取り扱うことはできず、同日に欠勤したことを理由としてされた本件給与減額は、違法・無効であり、本件訓告についても、同日の研究参加を内容とする職務命令は無効であって、本件訓告もまた、その前提を欠く理由のないもので、客観的に重大な瑕疵があるものとして違法かつ無効であるとされた例。
● 9月9日
- 湊 栄市 (北海道大学大学院)
- 社会福祉法人八雲会事件 函館地判 平成18年3月2日 労判913号13頁
- 国家公務員に準じて増額改定の利益を享受してきた民営事業所の職員が、官民格差の是正の趣旨でなされた人事院勧告に準拠した改定による賃金減額の不利益を甘受することについては、それ自体十分な合理性を有するものと言うべきであり、上記各改定の内容には社会的な相当性があるとされた例。
- 三浦 保紀 (北海道大学大学院)
- ウィシュ・神戸すくすく保育園事件 神戸地判 平成17年10月12日 労判906号5頁
- 保育士および所属する労働組合への被告法人の行為がいずれも不当労働行為に該当し、保育士2名と労働組合への損害賠償が認められた事例。
● 9月16日
- 所 浩代 (北海道大学大学院)
- 個人情報非訂正決定処分取消請求事件 〔上告審〕 最二小判 平成18年3月10日 判時1932号71頁
- 国民健康保険診療報酬明細書に記録された個人の診療に関する情報についてされた京都市個人情報保護条例に基づく個人情報の訂正をしない旨の決定が違法とはいえないとされた事例
- 同事件 〔控訴審〕 大阪高判 平成13年7月13日 判タ1101号92頁
- 個人情報保護条例に基づく個人情報の訂正請求を認めた事例
- 川久保 寛 (北海道大学大学院)
- 横浜市市立保育所廃止事件 横浜地判 平成18年5月22日 賃社1420号37頁
- 大東市立上三箇保育所事件 大阪高判 平成18年4月20日 賃社1423号62頁
- 大東市がその設置する市立保育所を廃止し民営化したことにつき、市と保護者の関係を公法上の利用契約関係ととらえ、市は、廃止にあたって十分な配慮を怠ったとして義務違反を認定し、慰謝料を認容した事例。
● 9月30日
- 斉藤 善久 (北海道大学助手)
- 三都企画建設事件 大阪地判 平成18年1月6日 労判913号49頁
- 原告派遣労働者の勤務状況が債務不履行に該当するとしてなされた派遣先の交代要請に基づき、派遣元である被告会社が原告に対して交代と就労中止を命じたことにつき、原告に派遣契約上の債務不履行事由はなかったとされた例。
- 開本 英幸 (弁護士)
- 大阪府労委(朝日放送〔大阪東通〕)事件 大阪地判 平成18年3月15日 労判915号94頁
- 労働組合法7条にいう「使用者」とは、一般に労働契約上の雇用主を言うが、ラジオ・テレビ放送会社A社と業務請負会社B社の社員であった原告X4との間に労働契約が存在しないことが、社員化等の要求を行わない旨の本社協定書からも明らかであるとされた例。
10月
● 10月7日
- 本久 洋一 (小樽商科大学)
- 企業買収と労組法上の使用者性
- 参考) 厚生労働省 「投資ファンド等により買収された企業の労使関係に関する研究会報告書」 労旬1631号56頁
- 参考) 本久洋一 「企業買収と労組法上の使用者性」 労旬1631号14頁(2006年)
- 参考) 本久洋一 「転籍元たる親会社の労組法上の使用者性」 法学セミナー
623号(2006年)
- 紺屋 博昭 (弘前大学)
- 〈労働関係〉を手掛かりに団交応諾義務を考える
―― アメリカ労使関係法の知見とは?
- 久慈 享 (北海道大学大学院)
- ノイズ研究所事件 〔控訴審〕 東京高判 平成18年6月22日 労働経済判例速報1942号3頁
- ノイズ研究所事件 〔第一審〕 横浜地川崎支判 平成16年2月26日 労働経済判例速報1942号20頁
● 10月14日
● 10月15日
● 10月21日
- 鈴木 真史 (北海道大学大学院)
- 八女労基署長(九州カネライト)事件 福岡地判 平成18年4月12日 労働判例916号20頁
- 業務と精神障害の発症,憎悪との因果関係の判断にあたっては,精神障害の発症の原因と見られる業務の内容,勤務状況、業務上の出来事等を総合的に検討し,当該労働者の従事していた業務に当該精神障害を発症させる一定以上の心理的負荷が認められるかを検討することが必要であるとされた例
- 戸谷 義治 (北海道大学大学院)
- アイビーエス石井スポーツ事件 大阪地判 平成17年11月4日 労経速1935号3頁
- 集団退職による営業妨害行為を理由とする懲戒解雇は有効であるとして,退職金請求を認めなかった例
- フラッグスファイブ・プロモーション事件 東京地判 平成17年10月28日 判時1936号87頁
- モデル等のマネージメント業務等を行う会社の取締役、従業員が競業する新会社を設立し,多数のモデル等を勧誘して移籍させた場合について,取締役等の不法行為責任、新会社の使用者責任が肯定された事例
● 10月28日
- 大石 玄 (北海道大学大学院)
- 近畿建設協会(傭止め)事件 京都地判 平成18年4月13日 労働判例917号59頁
- 同一業務・別形態での契約更新提案と,その後の雇用拒絶の可否
- 山田 哲
- 豊國工業事件 奈良地判 平成18年9月5日 判例集未登載)
- 被告が原告労働者の社会保険被保険者資格取得を各保険者に届け出る義務を怠ることは、被保険者資格を取得した労働者の法益をも直接に侵害する違法なものであり、労働契約上の債務不履行をも構成するとして、損害賠償請求が認容された例
11月
● 11月11日
- 開本 英幸 (弁護士)
- 淺野 高宏 (弁護士)
- 所 浩代 (北海道大学大学院)
- アメリカの労使関係における健康情報管理とプライバシー保護法理
- 平賀 律男 (北海道大学大学院)
- 安部 薫道 (北海道大学大学院)
- ネスレジャパンホールディング事件 最二小判 平成18年10月6日 公刊物未登載
● 11月18日
- 鈴木 真史 (北海道大学大学院)
- 富士電気E&C事件 名古屋地判 平成18年1月18日 労判918号65頁
- うつ病り患による休職後、職場復帰し、課長職として転勤・単身赴任した後に自殺したAにつき、転勤後にAのうつ病は完全寛解していたとされ、そのことに照らせば、管理職としての業務一般及びAが従事した個々の業務が、Aにとって、心理的負荷を及ぼすような過重な業務であったと認めることはできないとされた例。
- 参考) 名古屋南労基署長(中部電力)事件 名古屋地判 平成18年5月17日 労判918号14頁
- 三浦 保紀 (北海道大学大学院)
- 呉市(広島県教職員組合)事件 最三小判 平成18年2月7日 労判916号5頁
- 管理者は、教職員の職員団体にとって学校施設使用の必要性が大きいからと言って、職員団体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し、許容しなければならない義務を負うものではなく、使用を許さないことがその裁量権の逸脱又は、濫用と認められる場合を除き、違法となるものではないとされた例。
● 11月25日
- 久慈 享 (北海道大学大学院)
- ヤマト運輸事件 東京地判 平成18年4月7日 労判918号42頁
- 被告会社支店の荷さばき場で、被告従業員C運転のフォークリフトが原告業務委託会社従業員に衝突した事故につき、人と荷物ボックスの混み合う場所を、被告Cが後方を確認することなく、バック・ブザーも鳴らさずに走行したことには過失があり、使用者被告会社はCと連帯して、原告の怪我による損害賠償請求について不法行為責任を負うとされ、また当時支店長であった被告Aも、本件事故当時はまだ出勤していなかったとしても、構内現場の管理責任者として、Cと連帯して、損害賠償責任を負うとされ、被告会社、A,Cに1520万余円の支払いが命じられた例。
- 大石 玄 (北海道大学大学院)
- 地公災基金鹿児島県支部長(内之浦町教委職員)事件 最二小判 平成18年3月3日 労判919号5頁
- 心臓疾患が確たる発症因子が無くてもその自然の経過により心筋梗塞を発症させる寸前にまでは憎悪していなかったかどうか」について十分に審理することなく、死亡とバレー試合出場との間に相当因果関係はないとした原審判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして破棄(差戻し)された例。
12月
● 12月2日
- 関 芙佐子 (横浜国大)
- 旭川市介護保険条例訴訟 最三小判 平成18年3月28日 判時1930号80頁
- 介護保険法135条の規定による介護保険の第1号被保険者の保険料についての特別徴収の制度と憲法14条、25条。
- 道幸 哲也 (北海道大学)
● 12月9日
- 巽 敏夫 (社会保険労務士)
- クリスタル観光バス(賃金減額)事件 大阪地判 平成18年3月29日 労判919号42頁
- 買収された観光バス会社に運転士として就労している4名が本件買収後の労働条件の不利益変更の効力を争った事案。
- 佐久間 ひろみ (北海道大学大学院)
- 公務員労働の流動化にともなう諸問題――独立行政法人制度を手がかりに
- 戸谷 義治 (北海道大学大学院)
● 12月16日
- 岸 巧 (弁護士)
- 石山(賃金台帳提出命令)事件 東京高判 平成17年12月28日 労判915号107頁
- 賃金台帳につき提出を命じた原決定は結論において相当であるとして、抗告が棄却された例。
- 淺野 高宏 (弁護士)
- 協和出版販売事件 東京地判 平成18年3月24日 労判917号79頁
- 従来の55歳定年を60歳定年とし、併せて55歳に達した翌日から嘱託社員としてそれまでの賃金とは別の給与体系とする就業規則の変更が無効であるとしてなされた賃金差額及び時間外賃金の差額等の請求が棄却された例。
- 淺野高宏+岸巧+ 開本英幸 (弁護士)
▲ 先頭へ